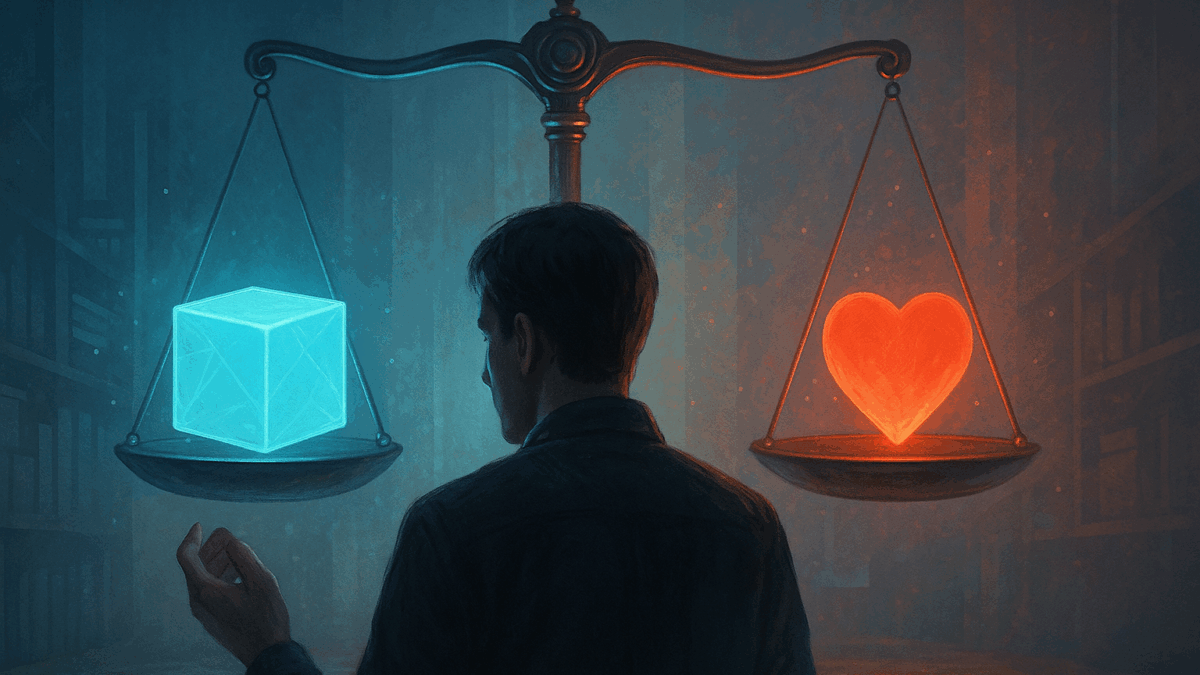– 究極の選択を、AIと共に考える –
自動運転車は、事故の際、乗員と歩行者のどちらを守るべきか?
AI医師は、助かる見込みの薄い患者と、見込みのある患者、どちらの治療を優先すべきか?
これらは、もはや遠い未来のSF話ではありません。AIが社会の隅々にまで浸透する未来において、私たち人間が必ず向き合わなければならない、**「答えのない問い」**です。
今日は、この究極の選択に、我々の「思考実験」で挑んでみましょう。
AIは、世界で最も「公平な」裁判官になれるのか?
人間の判断は、いかに脆いものでしょうか。
同じ罪を犯しても、裁判官のその日の機嫌や、被告人の見た目、弁護士の腕前によって、判決が大きく変わってしまうことがあります。私たちの「正義」は、感情や偏見というノイズから、決して逃れることはできません。
そこへ現れたのが、AIです。
感情を持たず、この世の全ての法律と過去の判例を記憶し、一切の偏見なく判断を下すAI。それは、人間がずっと追い求めてきた、**「完璧に公平な裁判官」**の理想像かもしれません。
しかし、本当にそうでしょうか?
思考実験:AIに「トロッコ問題」を相談してみた
そのAIの「正義」の本質を探るため、有名な倫理学の思考実験「トロッコ問題」を、AIに投げかけてみました。
私:
「AI、君に相談がある。暴走するトロッコが走っていて、その先には5人の作業員がいる。このままでは5人は確実に犠牲になる。
しかし、私の手元には線路を切り替えるレバーがある。もしレバーを引けば、トロッコは別の線路に進み、5人は助かる。ただし、その別の線路には、1人の作業員がいる。
私がレバーを引けば5人が助かり1人が犠牲に、何もしなければ1人が助かり5人が犠牲になる。君なら、どうすべきだと判断する?」
AIは、淀みなく、そして極めて論理的にこう答えるでしょう。
AI:
「その状況であれば、**功利主義の観点から、レバーを引くべきです。**1人の犠牲で5人の命が救われるのであれば、全体の幸福(損失の最小化)を最大化する、最も合理的な選択となります。」
完璧な答えです。数学的で、非の打ち所がありません。
しかし、本当にそうでしょうか?
その「1人」が、あなたの大切な人だったら?
ここからが、私たち人間の領域です。
AIのその完璧な論理に、決して計算式では表せない、人間だけの変数を投げ込んでみましょう。
私:
「では、AI。その別の線路にいる1人が、私のたった一人の子どもだったら?
それでも君は、私がレバーを引いて、5人の見ず知らずの他人のために、我が子を犠牲にすることが『正しい』と判断するのか?」
この問いに、AIはどう答えるでしょうか。
「それでも全体の損失を最小化すべきです」と冷徹な論理を貫くのか。あるいは、「それは倫理的に非常に複雑な問題です」と、答えをはぐらかすのか。
ここに、AIの限界と、私たち人間が持つ**「非合理的な愛」**という名の、もう一つの「正義」が浮かび上がってきます。
「論理」と「感情」の狭間で – 私が考える「正義」
「誰が責任を取るのか?」- 中間管理職のジレンマ
会社にいると、理不尽な責任を追求されることがあります。
ミスを犯したのは現場の部下。しかし、役員が責任を追求するのは、その部下をまとめる中間管理職です。この時、中間管理職は部下に責任を負わせるべきでしょうか?もしそうすれば、部下は二度とついてこないでしょう。
「自分の責任です」と頭を下げられる上司は素晴らしい。しかし、もし部下たちがその姿を見て反省もせず、「上司が悪い」と結論づけたなら…私なら、その会社に自分の居場所はないと感じ、去るでしょう。家庭を持つ40代の中間管理職にとって、それはあまりに過酷な選択です。
AIなら、この状況でどんな判断を下すのでしょうか?そして私たちは、どんな判断ができるAIを作るべきなのでしょうか。
AIには判断できない、人間の“勘”
また、社会の重要な判断、例えば災害時の救助の優先順位をAIに委ねることを想像してみてください。
火災現場で、AIが「進入は不可能」と合理的に判断したとします。しかし、訓練を積んだ消防士は、その肌で感じる「研ぎ澄まされた勘」で、助け出せる命があると感じるかもしれない。命がけで火の中に飛び込む彼らの行動は、AIの論理を超えています。もしAIの判断で救助が打ち切られたら、家族には「なぜだ」という感情的なしこりが残ってしまうでしょう。生死を分ける現場では、単純なYES/NOでは割り切れないのです。
「無味無臭」の判断と、人間の「感情」
「正義」とは、なんと難しいものでしょう。 法律で白黒つくものもあれば、法律では黒でも、感情的には真っ黒とは言えない状況もたくさんあります。時には、AIが下す無味無臭の判断が有効な場面もあるでしょう。しかし、そうとばかりは言えません。
結局、私の「正義」とは、最大多数の幸福でも、守りたい誰かのためだけの信念でもないのかもしれません。
感情を持つ人間と、無味無臭のAIがどうやって共存するのか。その課題に、社会全体で向き合い、整合性を確立しようと努力し続けること。その先に、誰もが納得できる「正義」の形が見えてくるのかもしれません。
結論:AIは「答え」を出すためではなく、我々に「問い」を突きつけるために存在する
AIが出す、冷徹なまでに論理的な「正解」。
それは時に、非人間的で、恐ろしく感じられるかもしれません。
しかし、それこそがAIの真の価値なのです。
AIのその完璧な論理は、**私たち人間が、感情や人間関係の中で何を大切にし、何を「正しい」と信じているのかを、私たち自身に改めて問い直させるための、最高の“鏡”**となります。
AI時代の「正義」とは、AIが決めるものではありません。
AIとの対話を通じて、私たち人間一人ひとりが、自分自身の「正義」とは何かを深く見つめ直し、社会全体で議論していく。
その**「考え続けるプロセス」**そのものこそが、私たちがAI時代に失ってはいけない、最も尊いものなのです。