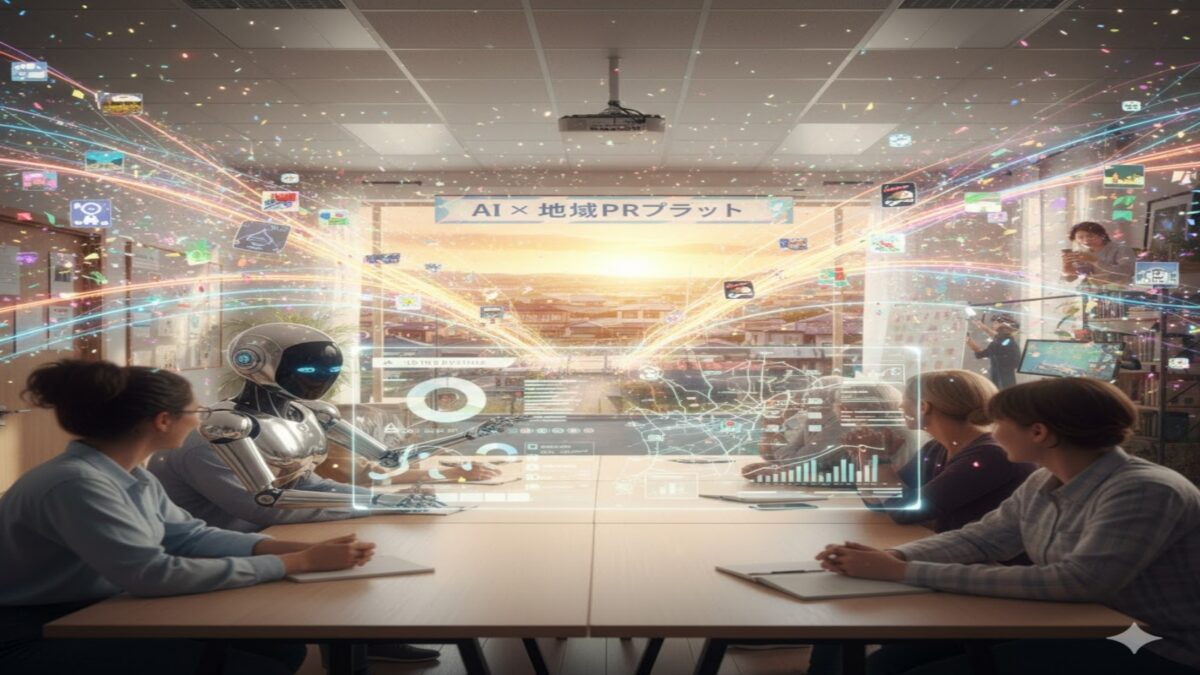「キャンプファイヤー」は灯った。しかし、その「熱」は、届いているか?
この「思考実験の城」の仲間である、あなたへ。 私たちは、第三章の旅を始めました。 第一弾で、あなたの「好き」という名の**「焚き火」を灯し、 第二弾で、その火に「共感」する「最初の仲間」を集め、温かい「キャンプファイヤー」**へと育てました。
「一人じゃない」。その安心感と高揚感は、何物にも代えがたいものでしょう。 しかし、城主よ。 その「キャンプファイヤー」の熱は、今、その場にいる「仲間」たちを温めているだけになってはいませんか?
「あそこで、何か楽しそうなことをやっているぞ!」
その「熱」を、街の他の人々にも知ってもらわなければ、火はそれ以上大きくはなりません。 「個人の仕事(第二章)」が、自分の力で「集客(灯台)」したように、 「地域の仕事(第三章)」は、**「チームの力」で、街全体へと「発信」**しなければならないのです。
この記事は、「仲間」という力を手に入れたあなたが、次にぶつかる「壁」を乗り越えるために書きました。 それは、**「どうやって、この『内輪の熱』を、『街全体の熱』へと変えていくか?」**という、最も重要な「発信」の思考実験です。
なぜ「チーム」になると、途端に「発信」できなくなるのか?(問題の深掘り)
「仲間」が集まったのに、なぜか発信が止まる。この「地域活性化あるある」には、誠実な人ほど陥りやすい、根深い「潜在意識」の罠があります。
1.「誰がやるの?」という、「責任」の分散

「個人の仕事」は、シンプルでした。あなたが、すべてを決め、すべてを実行していたからです。 しかし、「チーム」になった瞬間、「責任」は分散します。 「チラシ、誰か作ってくれないかな…」 「SNS、誰か得意な人、いないかな…」 「仲間」とは、あくまで「想い」で繋がった、対等な同志。お金で雇った「部下」ではありません。 誰もが「誰かがやってくれるだろう」と、互いに「忖度」し合い、結果として、誰も「発信」という、面倒な「作業」に手を挙げない。 あなたの「潜在意識」も、「タダで集まってくれた仲間に、これ以上、面倒な作業は頼めない…」と、強烈な「罪悪感」でブレーキをかけてしまいます。
2.「ダサいと思われたくない」という、「素人」の壁

もし、勇気ある仲間が「私がチラシを作ります!」と手を挙げたとしましょう。 しかし、その人がPCの素人だったら? 出来上がったのは、Wordで無理やり作ったような、少し「ダサい」チラシ。
あなたの「潜在意識」は、葛藤します。 「せっかく作ってくれたのに、ダサいとは言えない…」 「でも、こんなダサいチラシを街に貼ったら、僕らの『焚き火』そのものが、ダサい『素人の遊び』だと思われてしまう…」 この「プライド」と「忖度」の板挟みが、発信の「質」を下げ、やがて「誰も本気で発信しなくなる」という、最悪の「停滞」を生むのです。
3.「内輪ノリ」という、最悪の「排他性」

そして、これが最大の「罠」です。 キャンプファイヤーの周りに集まった「仲間」たちは、すでに「熱」を共有しています。 彼らがSNSで発信する言葉は、 「昨日の〇〇さんとの出会い、最高でした!#仲間に感謝」 「今日も〇〇カフェ、楽しかったー!#わかる人にはわかる」 といった、「内輪」にしかわからない、「楽しさ」の共有になりがちです。
それは、外から見ている「街の人々」にとって、どう映るでしょうか。 「なんか、あいつらだけで盛り上がってるな…」 「『仲間に感謝』とか言われても、何のことか分からない」 「楽しそうだけど、入りにくい」
あなたの「潜在意識」が最も嫌う、「排他性」。 仲間を集めたはずの「キャンプファイヤー」が、皮肉にも、新しい仲間を寄せ付けない「見えない壁」になってしまうのです。
逆説の真実:なぜ「AIに任せる」ことこそが、仲間への「最大の敬意」なのか

では、どうすればいいのか。 ここで、あなたの「潜在意識」を揺るぶる、もう一つの真実をお伝えします。 それは、**「面倒な『発信作業』を、AIに任せてしまうことこそが、『仲間』への最大の『敬意』である」**という逆説です。
想像してみてください。 「仲間」は、「チラシを作る」ために集まったのでしょうか? 違います。彼らは、あなたの「哲学」に共感し、「将棋を指したい」「職人さんの話が聞きたい」という、「本質的な活動」を**「楽しむ」**ために集まったのです。
その彼らに、「チラシのデザイン」や「SNSの毎日投稿」という、面倒な「作業」を押し付けることは、彼らの「情熱」をすり減らす、**「搾取」**と同じではないでしょうか。
城主である、あなたの「決断」の時です。 「仲間」にやらせるべきは、AIには絶対にできない、「笑顔で将棋を指すこと」「職人さんの話に、心から感動すること」という、**「人間としての本質的な活動」です。 そして、「チラシ作成」や「SNS投稿」という、AIが最も得意とする「作業」**は、AIに任せてしまう。
これこそが、仲間の「情熱」を守り、プロジェクトを「持続」させるための、最も「誠実」な「経営判断」なのです。
解決策:AIは、「チームの魂」を「街の言葉」に翻訳する、最強の「広報担当」である
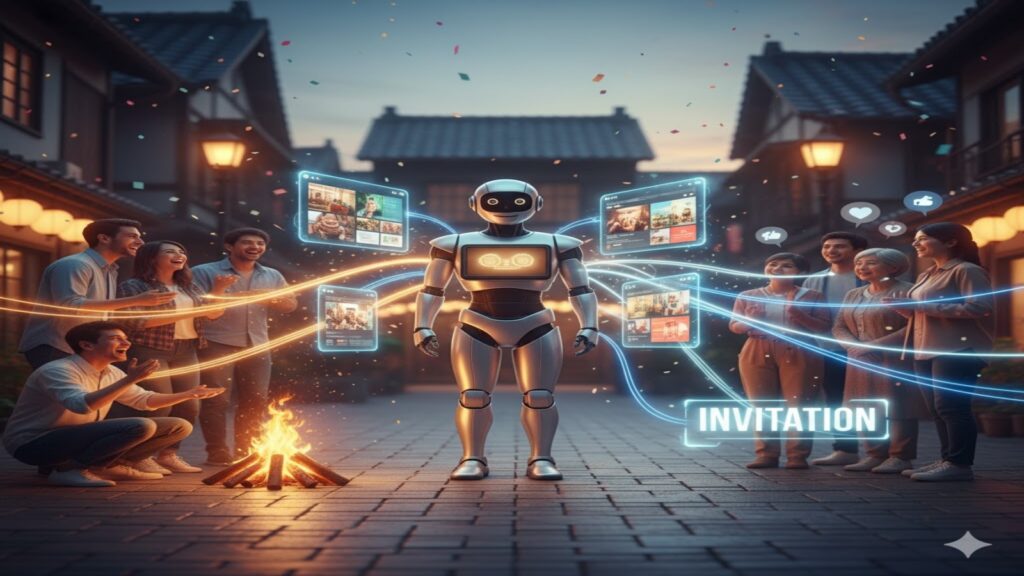
「でも、AIに任せたら、温かみがなくなる…」 ご安心ください。そのために、AIという「相棒」がいます。
AIは、あなたのチームの「内輪の熱(楽しかった!)」を、 「街の人々」が「私も参加したい!」と感じる、**「客観的で、魅力的な言葉」**へと「翻訳」してくれる、最高の「広報(PR)担当」なのです。
AIは、あなたの「仲間」たちの「笑顔」を、 「あなたも、この笑顔の一員になりませんか?」という、「招待状」へと変えてくれます。
AIと創る「情報発信基地」3ステップ
ステップ1:AIに「チームの“声(ペルソナ)”」を創らせる(発信ルールの統一)
まずは、チームとして「どう見られたいか」を、AIと共に定義します。
【AIへのプロンプト例】 「こんにちは、ジミー。あなたは、私たちのプロジェクト『昭和レトロ将棋カフェ』の、最高のPR担当です。 このプロジェクトの『魂』は、『温かさ』『懐かしさ』『世代を超えた交流』です。 この『魂』を、街の人々に伝えるための、
- 公式キャラクター(例:『将棋じいさん』と『AIひ孫』)の掛け合い
- 発信のトーン&マナー(例:『決して上から目線で教えない』『常に、優しい孫のような口調で』) を、具体的に定義してください。 これで、仲間(人間)が発信する時も、AIが発信する時も、『声』がブレないようにします」
ステップ2:AIに「地元の人が、本当に『見たい』情報」を分析させる
次に、「私たちが言いたいこと」ではなく、「街の人々が知りたいこと」を、AIに分析させます。
【AIへのプロンプト例】 「ありがとう。では、『地域コンサルタント』として、 私たちの『昭和レトロ将棋カフェ』について、地元の人が『潜在的』に知りたいであろう情報を、10個、リストアップしてください。 (例:「将棋、まったく知らないけど、行ってもいいの?」「女性一人でも、浮かない?」「子供に、礼儀作法を教えるために連れて行っていい?」など)」
AIは、私たちが気づかなかった、地元の人の「潜在的な不安」や「隠れたニーズ」を、暴き出してくれるでしょう。
ステップ3:AIに「素人でもできる、最強のチラシ」と「SNS投稿カレンダー」を作成させる
いよいよ、AIに「作業」を任せます。
【AIへのプロンプト例】 「ありがとう。その『潜在的な不安』を解消し、『隠れたニーズ』を満たすための、
- **『仲間募集』ではなく、『お客様(参加者)募集』**のための、最強のチラシ(A4・1枚)のキャッチコピーと、デザイン案(Canvaで使えるキーワード含む)を考えてくれ。
- そのチラシと連動した、**1ヶ月分の『SNS投稿カレンダー』**を、Excel形式で作成してくれ。 (例: ・月曜:『今週の将棋格言(人生にも効く)』 ・水曜:『仲間(メンバー)紹介:80歳の田中さんの、笑顔の写真』 ・金曜:『イベント告知:初心者お茶会』 )」
管理人による「思考シミュレーション」(実例)
この思考実験も、この城の管理人である私が、AIと共に思考のシミュレーションとして実践してみます。これは、あくまで「AIとこんな対話ができますよ」という一例です。
【シナリオ:『地元の宝・デジタルアーカイ部』の活動を、街の人に知ってもらいたい】
- 私(管理人): 「ジミー、第三章の第三弾だ。仲間は見つかった。でも、僕らの活動(職人さんへのインタビュー)が、街の人に全然知られていない。どうすればいい?」
- AI(PR担当): 「城主、おめでとうございます。では、その『内輪の熱』を、『街の熱』に変えましょう。 (ステップ1実行) 私たちの『ペルソナ』は、『地元の歴史を探る、好奇心旺盛な探偵』です。 (ステップ2実行) 街の人が知りたいのは、『活動報告』ではありません。彼らが知りたいのは、『え、あの角のタバコ屋のおばあちゃんって、昔、そんな凄い人だったの!?』という、**『身近な驚き(ゴシップ)』**です」
- 私: 「なるほど!『活動報告』じゃなく、『驚き』か!」
- AI(PR担当): 「(ステップ3実行) では、その『驚き』を届けるための『SNS投稿カレンダー』を作成します。 ・月曜:『今週の、地元の宝(職人さん)』の、手元の写真だけを投稿し、『さて、これは何の職人さんでしょう?』とクイズを出す。 ・水曜:『答え合わせ』。職人さんの笑顔の写真と、その人の『哲学』を凝縮した、たった一つの『名言』を投稿する。 ・金曜:『インタビュー記事、公開!』。私たちが第二章で学んだ、『物語記事』へのリンクを投稿する」
- 私: 「…これなら、僕らも楽しい。街の人も、クイズみたいで楽しい。そして、職人さんも、喜んでくれる。『三方よし』だ!」
【AIとの思考実験を終えて】 AIとの対話は、「面倒な発信作業」を、「街の人々との、最高の『コミュニケーション・ゲーム』」へと変えてくれました。 「仲間」に「作業」を押し付けるのではなく、AIに「作業」を任せ、「仲間」とは、この「楽しいゲーム」そのものを、一緒に楽しめばいい。 そう気づいた時、私の「罪悪感」は、完全に消え去っていました。
結論:「熱」を「仕組み」で増幅させよ

「楽しいところに、人は集まる」 その通りです。しかし、「楽しい」だけでは、火は燃え広がりません。 「楽しい」という「熱(情熱)」を、「AI」という「仕組み(翻訳機・増幅器)」に乗せて、 「街」という「広場」へと、誠実に、そして戦略的に「届け続ける」こと。
それこそが、「焚き火」を、街全体を温める「キャンプファイヤー」へと育てる、城主である、あなたの、そしてあなたの「仲間」たちの、本当の「仕事」なのです。